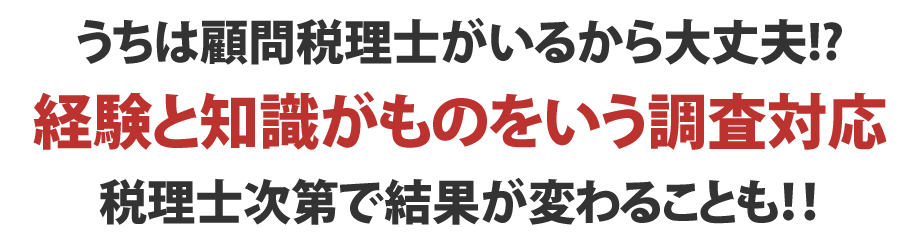

調査官の指摘が間違っていても反論しない税理士が存在する理由
調査官のしてきに誤りがあっても反論しない税理士が存在する理由、それは税理士と税務署の関係にあります。
一般的には開業して3年以上の税理士(会計事務所)であれば、30以上の顧問先を持っています。
そして、税理士は顧問先の税務申告を代理で行い、
税務署も申告書等により申告者の顧問税理士をすべて把握することができます。
つまり、どういうことかというと、税務調査で税理士が税務署に目をつけられた場合には、
税理士の顧問先であるクライアントすべてに税務調査が入るということが考えられる訳です。
そうなると、税理士側の対応が大変なのはもちろん、顧問先にも迷惑がかかります。
単純に税務調査が入ることって、そんなに大変なの?
と思う方もいるかもしれませんが、これは実際に体験した方しかわかりませんが、
小規模で1日で終了するような調査を除けば、少なからず、経営者や経理担当者の時間が調査のために割かれることが多いため、
通常の業務にも少なからず影響がでているといってほぼ間違いありません。
さらに、調査が長引いた場合には大きな影響がでることも珍しくありません。
もちろん、すべての地域でこのような実態があるかどうかは別にしても、
税務署で働いていた方などから、実際に税務署には税理士格付けリストなるものがあるということは耳にすることがありますので、
あながち、単なる噂というわけでなさそうです。
このような背景から調査において反論することが調査官の心証を悪くすると勘違いしている税理士がいるのかもしれません。
実際には、調査官の間違った指摘に論理的に反論することで税務署との関係が悪くなることはありません。
強いて、反論をすることで調査官の心証に影響があるとすれば、反論が感情的なものだったり、反論の言い方の問題でしょう。
今回の調査を無理に乗り切ってもどうせ来年以降の調査で持っていかれる?
前述したように、税務署との良好な関係を優先しているために、調査で反論しない税理士がいるとお伝えしましたが、
このような調査で税務署側につく税理士が決まって言うことがあります。
「税務署に楯突いて今回の調査を上手く乗り切っても、
税務署に目をつけられたら来年以降にまた調査が入って、もっと持っていかれるから、
税務署の指摘には従っておくことが無難だよ。」
これは半分は正しく、半分は税理士自身を守るための発言だと言えます。
税理士自身を守るための発言というのは、税理士自身が税務署から目をつけられたくないということです。
では、半分正しいというのはどういうことか。
それは、税務調査は論理的な反論と交渉で、税務調査官や税務署も納得する着地であったかどうかが問題になります。
まず大前提として、調査官が本来重加算税の対象でないものを重加算税対象として提示したり、
推定課税が適用できないはずのところを推定課税の適用を強要してくるということがあるため、
調査官の中にはとりあえず提示してみて反論してきたら詳しく聞いていこうというスタンスの方もいて、
調査官も否認した内容や提示した課税内容がすべて了承されると思っていないケースもあるということです。
だからこそ、双方の納得する着地という表現を使っていますので、この点はご理解した上でお読みください。
次に、最近ニュースなどで話題にもなっていますが、国税庁や税務署のOBの税理士で現職時代の人脈やコネを利用することで、
税務調査に不当に抑えたり、回避したりすることが問題になっています。
このような不適正かつ非論理的な方法で調査対応をして強引に抑えてしまった場合には、
いずれ調査で同じ指摘を受けてしまう可能性が大きいです。
もちろん、その際には延滞税も増えていますし、その税理士のやっていることは違法行為です。
ここで強調しておきたいのは、上記は極端な例で、このような対応手法を使う税理士はごくわずかであり、
ほぼすべての国税庁や税務署のOB税理士は適正な対応をしているということです。
話がそれましたが、半分正しいというのは、上記の例ほど極端ではないにしろ、
不適正かつ非論理的な反論と交渉によって抑えられた調査で、税務署も納得できる着地ではない場合には、
翌年に税務調査が入って、大きな痛手を受けたという例が実際にあるからです。
この話にはもう一つポイントがあり、今回の調査を税務署の指摘が重加算税の対象だとすると、
税理士の顔色が一気に変わるかもしれません。
重加算税が課されてしまった場合には、税務署の指摘通りに修正申告したとしても、
翌年以降も税務署から要チェック納税者としてマークされることになります。
つまり、最悪のケースとして毎年調査に入ることさえ、ありえるということです。
だとすれば、重加算税の対象となる顧問先は持ちたくないというのが税理士の心理です。
税務調査で重加算税が課される割合は「20.6%」、5件に1件が重加算税の対象に!!
何度も繰り返しお伝えしていますが、税務調査において、約20%が重加算税になっているということは、衝撃的な事実です。
税理士が顧問についている割合から考えてもこの数字は異常です。
この中には本来重加算税対象ではない、かつ顧問税理士がいるのに、
結果として重加算税を課されたという例もかなりの数であるはずです。
もちろん、脱税の意図(仮装や隠ぺい)があった場合を除いて考えるにしても、
「税理士の交渉力」「税務調査官の評価制度」の2つがこのような結果につながっていると言えます。
まずひとつめは、前述しているとおり、税務署に反論できない税理士が存在するということ。
何でもかんでも調査官の指摘に反論するのはお門違いですが、適正な申告を行っているにも関わらず、
税務署との関係を気にするがゆえに、調査官の誤った指摘さえ、鵜呑みにしてしまう税理士が意外に多いという現実。
そして、もう一つが調査官の評価制度の問題です。
調査官は、重加算税を課した割合=不正発見割合で評価されています。
調査官が自分の評価を上げたければ、どんな否認指摘にでもとりあえず「重加算税ですね」と言っておいて、
反論されなければ重加算税を課してしまうというのが現実です。
万が一、税理士がしっかり反論してくれなかったら、重加算税を課されてしまいます。
重加算税が課されるかどうか微妙な状況であれば、税理士次第で結果が大きく変わってしまうかもしれません。
税務調査専門の税理士には調査のみの対応で顧問を変える必要がないという税理士も!!
顧問税理士にちょっと頼り無さや不安を感じても、顧問契約を切り替えるというほどの不満を感じていないという場合には、
税務調査だけの対応を依頼できる専門税理士やセカンドオピニオンとして税務調査に協力してもらえる専門税理士もいます。
このような税理士に依頼すれば、顧問税理士を変更することなく、税務調査を乗り切るためだけに専門税理士に力を借りることができます。